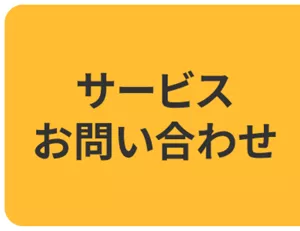しっかり食べて内臓脂肪をためにくい食事法「スマート和食」。
“がまん”しなくていい秘密や、毎日のくらしに取り入れるコツをご紹介します。
※「スマート和食」は、花王の登録商標です。

何をどう食べるかによって、同じカロリーでも内臓脂肪のつき方に差があることを発見!重要なのはカロリーだけでなく、栄養素のバランス(比)だったのです。花王は、内臓脂肪をためない、3組の栄養素の比を見いだしました。




タンパク質は筋肉を維持し、代謝の高いカラダづくりのため積極的に摂りたい栄養素。けれど、肉でタンパク質を摂ろうとすると、脂身がついてきたり、揚げる・炒めるなどの調理で結果的に、脂質が多くなりがちに。脂質を減らしながらタンパク質を増やす意識で摂取するのが大切です。






炭水化物は糖質と食物繊維から構成されており、糖質はカラダを動かすエネルギーになります。とはいえ、パンやお菓子など、食物繊維が少なく糖質が多い食べ物は、血糖値の急上昇などを招き、カラダに脂肪がたまりやすくなる面も。糖質を摂取するときは、食物繊維をいっしょに摂ることが重要です。



肥満や脂質異常症(高脂血症)などの原因となる脂質。減らしたい栄養素ではありますが、カラダに必要なものでもあるため、選んで摂取することが大切。飽和脂肪酸(肉や乳製品に多く含まれる)は減らし、内臓脂肪になりにくいオメガ3(青魚に多く含まれるDHA、EPAなど)を積極的に摂りましょう。
上の図の栄養素の比を意識した食べ方をすると、食べる量を減らさなくても内臓脂肪がつきにくくなり、誰でもGENKIな生活を送ることができます。3組の比のうち、どれかひとつからでも取り入れ始めればOK!「しっかり食べて太りにくい」スマート和食は、手軽かつ、「しっかり食べるから続けられる」食事法でもあるのです。

栄養バランスを“比”で考える理由は、食材には複数の栄養素が含まれているから。一つの栄養素だけに注目すると、その食材に含まれている他の栄養素の存在を忘れて、結果的に栄養バランスが崩れがちになります。身近な食材である「肉」を例に“比”の考え方をお伝えします。
例えば「ステーキはタンパク質たっぷり!」と思って食べたら、実は脂質の方が多かった…というように、一口に「肉」と言っても種類や部位によってタンパク質と脂質の“比”に差があります。同じ100gでも、和牛カルビはカロリーの10%がタンパク質で、残りの90%は脂肪ですが、鶏むね肉(皮なし)やささみはその逆で、ほとんどがタンパク質。カロリーも和牛カルビの約1/5です。できるだけ脂質が少なくタンパク質が多い肉(下のグラフの右のほう)を選ぶのがオススメ。脂質の多い肉を選ぶ場合は、調理や食べる際に脂身や皮を取ると、脂質とカロリーがぐんと減り、スマート和食に近づきます。




出典:「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」より作図
また、糖質と食物繊維をいっしょに摂る(※前出「比2」参照)比の考え方は、「糖質を内臓脂肪に変えない」のが目的。副菜として野菜をつける、主食ではご飯に玄米や麦、雑穀米を混ぜ、食物繊維量をアップさせるなどで、結果、内臓脂肪減少へ。内臓脂肪になりにくいといわれているオメガ3を含む魚は1日1回を目標に(※前出「比3」参照)。特にイワシやサバなどの青魚にオメガ3は豊富に含まれています。栄養素を丸ごと摂取できる、ブイヤベースなどのスープや小麦粉をつけたムニエルなどはオススメです。
ご紹介した“3組の比”の考え方は、毎食実践できなくても、1日のうち1食だっていいのです。買い物のときや調理の際に、無理のない範囲で取り組み続けて、習慣化することが重要です!

メニューの選び方を工夫するだけで、どこでもスマート和食の実践は可能!外出時のランチや飲み会、コンビニやスーパーでのお弁当選びなど…“比” の考え方があれば、いつでも始められます。
まずはよく食べるメニューの栄養表示を見てみてください!タンパク質と脂質はどちらが多いですか?
*中食とは…
コンビニエンスストアやスーパーなどでお弁当や惣菜などを購入したり、デリバリー(宅配・出前)などを利用して、家庭外で調理・加工されたものを購入して食べる食事をさします。
[参考:中食の選び方/厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイト]
「スマート和食」外食&中食時の基本

脂質が少なく、タンパク質の多いものを!

主食や主菜にタンパク質が少ない場合は…
→タンパク質が多い副菜と、食物繊維が多い副菜を!(脂質は少ないものを!)
タンパク質が多い主食や主菜の場合は…
→食物繊維が多く脂質の少ない副菜を!




チーズハンバーグドリア
子ども大人問わず人気の定番洋食メニューですが、タンパク質と脂質のバランスが少々偏りがち…。

ローストビーフ丼
GOOD POINT
・主食・主菜
脂質が少なく、タンパク質が多いものを選んで!

ローストビーフ丼、きのこのソテー、海藻サラダ
GOOD POINT
・副菜
キノコのソテーと海藻サラダで食物繊維アップ。食物繊維の比を上げる、スマート和食の優等生メニュー。




ツナマヨおにぎり、インスタントラーメン
サッと済ませたいときに重宝する、お手軽セット。しかし、脂質量が気になるところ…。

シャケおにぎり、鳥のつくね焼き
GOOD POINT
・主食
脂質の低い具材のおにぎりをセレクト!
・主菜
インスタントラーメンより脂質が少なく、タンパク質が多い主菜にして、内臓脂肪の蓄積をブロック!

シャケおにぎり、鳥のつくね焼き、ひじきの煮物
GOOD POINT
・副菜
ひじきの煮物をプラスし、糖質+食物繊維の法則もカバー!
まずは主食や主菜のメニュー選びから、スマート和食を始めてみるのはいかがでしょうか?慣れてきたら、脂質や食物繊維に気を配りながら、副菜を1品、2品と増やして、より栄養バランスの取れた“スマート和食メニュー”を目指しましょう。