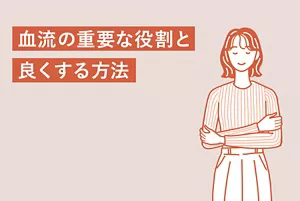- ヘルスケアナビTOP
- 症状ケア
- 風邪予防の基本!原因から生活習慣・初期ケアまで紹介

風邪予防の基本!原因から生活習慣・初期ケアまで紹介
この記事の監修者
芝大門いまづクリニック院長
今津 嘉宏さん

消化器外科医としての経験を経て、漢方や生活習慣改善を取り入れた統合医療を実践。免疫力を高め、風邪や体調不良を防ぐ日常ケアを大切にしている。著書に「風邪予防、虚弱体質改善から始める 最強の免疫力」「病気知らずの名医が食べている 長生き朝ごはん」(いずれもワニブックス)などがある。
1.風邪のおもな原因はウイルスによる感染

風邪の症状はさまざまだが、一般的にはのどや鼻に現れることが多い。
【風邪のおもな初期症状】
-
・のどのイガイガや軽い痛み
-
・鼻水、鼻づまり
-
・くしゃみ
-
・悪寒
-
・軽い倦怠感
これは、のどや鼻は空気の通り道で、ウイルスの侵入口になりやすいから。付着したウイルスが炎症を起こすことで、のどの不快感や痛み、鼻づまりなどの初期症状が出る。その後、ウイルスの増殖にともなって悪寒、倦怠感へとつながっていく。
風邪の原因となるウイルスは100種類以上存在する。代表的なのはライノウイルス。さらに一部のコロナウイルスもいわゆる風邪として症状をもたらす。感染経路は、咳やくしゃみによる飛沫感染と、空気中に漂うウイルスを吸い込む空気感染、手指を介して鼻や口、目に運ばれる接触感染の3つがある。
2.外側から風邪を予防する方法
-
・室温は20〜25℃・湿度は40%以上を目安にする
-
・手洗い・うがいを習慣にする
-
・人が多い場所ではマスクをする
室温は20〜25℃・湿度は40%以上を目安にする

一般的に室温は20〜25℃がよいとされるが、実際には住んでいる地域の気候や習慣、個人の体質によって適切な温度は異なる。温度ばかりを気にせず、「自分が快適に感じられるかどうか」を基準にするとよい。
一方で、湿度は感染予防に直結する。湿度の理想は60%前後だが、目安として40%以上でOK。エアコンが常時稼働していて換気が充分ではないと、家具や壁紙などが乾燥してしまうため、室内での湿度管理は難しくなる(加湿器に表示される湿度と部屋の中の湿度には、差があるので注意が必要)。
湿度が40%を下回るとウイルスは空気中を漂いやすくなり、粘膜も乾燥して感染しやすい状態になる。逆に湿度が40%以上に保たれると、ウイルスに水分が付着し、空気中を浮遊せずに落下する。さらに喉や鼻の粘膜が潤い、防御機能も高まる。
手洗い・うがいを習慣にする
ウイルスは手の指を介して体内に侵入しやすい。そのため、手洗いやうがいを習慣化できれば、感染をおさえることができる。
外出から戻ったときや手が明らかに汚れているときは石けんを使ってしっかりと洗うが、頻繁に石けんを使いすぎると皮膚を守る油分まで流れてしまう。こまめに洗う場合は流水だけでも効果がある。
【手洗いのタイミング】
-
・帰宅時
-
・食事の前後
-
・調理前
-
・不特定多数の人がよく触る場所を触ったあと
【うがいのタイミング】
-
・寝起き
-
・食事の前後
-
・人と会話した後
ウイルスによっては、のどの粘膜に付着して数分程度で感染が成立することもある。そのため、うがいだけでは完全に風邪を防ぐことはできない。しかし、うがいにはのどを潤し、粘膜の防御機能を保つ役割もある。だからこそ、「できるタイミングでうがいをする」ことが大事。
人が多い場所ではマスクをする
人が密集する場所では、飛沫感染と空気感染のリスクが高まる。マスクは相手からの飛沫を防ぐだけでなく、自分の咳やくしゃみで周囲に風邪をうつさないための「エチケット」としての役割がある。マスクで100%感染を防げるわけではないが、リスクを下げる方法の1つ。
マスクは鼻と口を覆い、隙間ができないように着けることが重要。あごの下まで覆い、鼻を出さないようにするだけでも予防効果は大きく変わる。

風邪予防の基本はシンプルです。温度と湿度を快適に保つ、手洗いやうがいを習慣にする、人混みではマスクをつける。この3つを続けるだけで十分効果があります。
3.内側から風邪を引きにくい身体をつくる方法
-
・3食しっかり、身体を温める食事をとる
-
・規則正しいリズムで質のよい睡眠をとる
-
・毎日30分程度、適度に身体を動かす
-
・ストレスをためこなまい
3食しっかり、身体を温める食事をとる

3食きちんと食べることで免疫の働きを支えるエネルギーが補われ、体力が維持される。とくに朝食は1日の中で最も重要であり、身体を目覚めさせ体温を上げる役割を持つ。
免疫力を高めるには、身体を温める食べ物を摂取することも大切。しょうが・ねぎ・にら・にんにくなど身体を温める食材を食べて、体温を上げることで、免疫細胞の働きが活発になる。
規則正しいリズムで質のよい睡眠をとる

睡眠は時間の長さだけでなく、質やリズムも重要。
毎日できるだけ同じ時間に寝て、同じ時間に起きることで、自律神経が安定して免疫機能が働きやすくなる。
人間は体温が下がると自然に眠気が訪れる。そのため、寝る前に身体を温めることで体温が下がる幅ができて、睡眠の質が高まる。就寝の1時間30分~2時間ほど前に湯船に浸かって入浴すれば、入浴後1時間ほどは体温が高い状態が続き、その後の体温低下とともに深い眠りに入りやすくなる。少し早い時間帯での入浴だったとしても、湯冷めしないようにしていれば効果は期待できる。
また、よい眠りに入るためには、寝る前のスマートフォンはできるだけ避けよう。強い光の刺激が脳を覚醒させ、自然な眠気を妨げる。
【睡眠の質を高めるポイント】
-
・規則正しい睡眠リズムを作る
-
・身体を温めてから寝る習慣をつける
-
・布団に入ってからはスマホは見ない
毎日30分程度、適度に身体を動かす

適度な運動は代謝を高め、免疫を活性化させるが、やりすぎは逆効果。過度な運動は疲労やケガを招き、かえってストレスとなる。逆に運動不足は体力を低下させ、気力の減退にもつながる。
毎日続けることが大切なので、運動習慣がない人は、まずは生活の中で身体を動かす工夫から始めてみよう。エスカレーターではなく階段を使う、通勤や買い物で歩く距離を少し増やす、家事や掃除を運動と考えるなど、小さな積み重ねが体力を支える運動習慣につながる。
厚生労働省の最新の考え方でも、ウォーキングに加えて家事や通勤といった日常生活の活動を含めて身体を動かすことが推奨されている。まずは毎日30分程度、生活の中で体を動かすことが目安になる。
ストレスをためこまない

ストレスは誰にとっても避けられないもの。短期間の緊張は問題ないが、慢性的に続くと自律神経が乱れ、免疫力を下げてしまう。風邪をひきやすくなる背景には、この慢性ストレスが関わっている場合がある。
大切なのは、ストレスを完全になくそうとするのではなく、「緊張」と「リラックス」のバランスをとること。趣味に没頭する、友人とおしゃべりを楽しむ、おいしいものを味わうなど、自分が心からリラックスできる時間を持つことが効果的。ときには自分へのごほうびを忘れず、心身をゆるめる習慣を持つとよい。

食事・睡眠・運動・ストレスの4つをコントロールできれば、免疫力は上がります。毎日の生活の中でできる範囲で少しずつ身体にいいことを続けるのが、一番の風邪予防になりますよ。
4.体調管理には「炭酸浴」がいいって本当?
炭酸浴とは、炭酸ガスを溶かしたお湯に浸かる入浴法。

炭酸入浴剤をお湯に溶かすと、炭酸ガスが発生する。この炭酸が皮膚から浸透し、血管を拡張させて全身の血流を良くすることで、酸素や栄養素を全身に届けてくれる。
血流が整うことで、自律神経のバランスが整い、心身のリラックスにもつながる。さらに、炭酸浴は深部体温のリズムに反動をつけることができ、自然な眠気と深い睡眠が誘発される。
これにより、質のよい睡眠が得られ、結果として風邪をひきにくい身体をつくることができる。
本来こうした効果はぬるめの湯に10〜15分程度浸かることで得られるが、炭酸浴では短時間でも同様の効果が得られるため、忙しい人に適した入浴法と言える。
注意点としては、長い時間湯船に浸かると「のぼせ」などにつながること。湯温は42℃を超えない範囲で、心地よく感じる温度を目安にしよう。

入浴で大切なのは、自分が気持ちいいと感じる温度と時間で入浴することです。毎日お湯に浸かることで、風邪をひきにくい身体づくりにつながります。週に一度、炭酸浴を「ごほうび入浴」として取り入れるのもよいでしょう。
5.風邪を引き始めたときの対策

-
・自分のサインを見極めて早めに対処する
-
・しっかりと身体を休め、必要に応じて薬を使う
自分のサインを見極めて早めに対処する
風邪の引き始めの症状は人によって異なる。のどのイガイガや鼻づまりなど「自分にとっていつも出るサイン」を知っておくことが大切。違和感を覚えたら早めに休養をとり、身体を冷やさないよう注意する。
しっかりと身体を休め、必要に応じて薬を使う
基本はしっかりと休むことが大事になるため、睡眠を十分にとって安静にしよう。
プラスして、身体を温める習慣を意識して冷やさないことも重要。ねぎやしょうがなど身体を温める食材を食べたり、首・手首・足首など太い血管がある部位を温めることで、効率的に身体全体を温められる。湯船に浸かれるなら入浴もしてよいが、湯冷めに注意しよう。
市販の総合感冒薬は初期症状の緩和に有効。かかりつけ医や行きつけの薬局の薬剤師に、風邪の初期症状について相談しておき、市販薬の服用や医者にかかった方がよいタイミングについて把握しておくと安心。
6.風邪に関するQ&A
風邪という病気はないって本当?
A.医学的に「風邪」という明確な病名はない。

さまざまなウイルスによる感染症の総称で、正式には「感冒」や「急性上気道炎」と呼ばれています。共通認識として理解しやすい便利な言葉なため、日常的によく使われています。
風邪をひきやすい人や習慣はある?
A.風邪のひきやすさは体質にもよるが、それ以上に日頃の生活習慣が関係している。

具体的に風邪を引きやすい習慣としては、以下があります。
・口呼吸
・身体が冷えやすい服装や食事
・入浴習慣があまりない
生活習慣を整えることで、風邪にかかりにくい身体をつくることができます。
- ヘルスケアナビTOP
- 症状ケア
- 風邪予防の基本!原因から生活習慣・初期ケアまで紹介